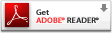記事一覧
パネライの3シリーズ、どれが自分に合うのか?2026年徹底比較
パネライの3シリーズ、どれが自分に合うのか?2026年徹底比較
「イタリアの軍事遺産を現代に継ぐパネライ——
その代表作であるラジオミール・ルミノール・サブマーシブルは、
パネライコピー見た目だけでなく、デザイン哲学と用途が明確に分かれている。
果たして、あなたのライフスタイルに最も寄り添うのはどれか?」
■ ① ラジオミール(Radiomir)—— 復古美の原点
- 誕生:1936年、イタリア海軍蛙人部隊向け
- 特徴:
- 枕型ケース(無護橋)
- 線状ワイヤーラグ(後期モデルは溶接式ラグに進化)
- “カリフォルニア文字盤”(ローマ+アラビア数字混合)
- 防水:100m
- 素材:ステンレス、チタン、Goldtech™レッドゴールド、セラミック
- 代表モデル:PAM00249(カリフォルニア)、PAM00655(Radiomir 1940)
💬 「これは“工具”ではなく、“歴史を纏う装飾品”」
■ ② ルミノール(Luminor)—— 護橋が象徴する現代的アイコン
- 誕生:1950年代、トリチウム夜光技術「LUMINOR」採用
- 特徴:
- 一体鍛造枕型ケース
- 大型表冠護橋(ブランド最大の識別要素)
- サンドイッチ文字盤(夜光塗料を2層で挟み込む構造)
- 防水:500m(2026年新作 Luminor Marina PAM03312)
- 新機芯:P.980 自動巻き(72時間パワーリザーブ、ストップ秒針機能)
- サイズ:44mm(復刻的な大径回帰)
💬 「護橋は機能ではなく、“存在宣言”だ」
■ ③ サブマーシブル(Submersible)—— 技術革新の最前線
- 起源:1998年(当初はルミノールの特別版:PAM00024)
- 独立:2019年、専門ダイバーズとして単独シリーズ化
- 特徴:
- ルミノールの護橋+単方向回転ベゼル
- 3時位置に日付拡大レンズ
- 防水300m以上(一部モデルは500m)
- 技術実験場:
- PAM01800 Elux LAB-ID(2024年):
- 機械エネルギーでLED発光(約30分持続)
- 動力残量表示付き
💬 「サブマーシブルは、パネライが未来へ向かう“窓”」
■ 編集部コメント:選ぶのは“時計”ではなく“態度”
「パネライの3シリーズは、単なるデザイン差ではない。
- ラジオミールを選ぶ人は、歴史と静謐な佇まいを愛する
- ルミノールを選ぶ人は、アイコニックな存在感を求める
- サブマーシブルを選ぶ人は、冒険と技術への好奇心を持っている
2026年、パネライは“大きくて目立つ時計”から、
“自分の哲学を映す道具” へと進化している。」
- 2026年01月23日(金)17時22分
曜日表示付き腕時計は、本当に日常で役立つのか?2026年おすすめ3選
曜日表示付き腕時計は、本当に日常で役立つのか?2026年おすすめ3選
スーパーコピー時計「“今日は何曜日?”——この一言が、意外と頻繁に頭をよぎる。
そんな現代人のため、IWCシャフハウゼン・タグ・ホイヤー・ゼニスが提案する、
実用性と機械美を兼ね備えた曜日表示モデルが注目されている。」
■ ① IWCシャフハウゼン パイロット・ウォッチ クロノグラフ IW388305
—— 飛行士のための情報表示
- ケース:41.1mm × 14.8mm、チタン(軽量かつ耐摩耗)
- 文字盤:ブラック+アラビア数字インデックス+夜光針
- 機能:3時位置に曜日・日付表示、3眼クロノグラフ
- ムーブメント:Cal. 69385 自動巻き(導柱輪式、46時間パワーリザーブ)
- 防水:100m
- 公定価格:¥80,400 → 約179万円
💬 「パイロットが瞬時に状況を把握するための、合理的な情報レイアウト」
■ ② タグ・ホイヤー カレラ キャリバー31 WDA2111.BD0001
—— シンプルさが生む汎用性
- ケース:41mm × 12.57mm、ステンレス×ゴールド(バイメタル)
- 文字盤:ブラック蛋白石(マット感のある深み)
- 機能:曜日・日付ウィンドウのみ(サブダイアルなし)
- ムーブメント:TH31-02 自動巻き(80時間パワーリザーブ)
- 防水:100m
- 公定価格:¥66,100 → 約147万円
💬 「余計な装飾を排し、必要な情報だけを届ける“通勤最適解”」
■ ③ ゼニス チャロン・フォレスト 03.3400.3610/38.M3200
—— 複雑機能のフルパッケージ
- ケース:38mm、ステンレス
- 文字盤:シルバーパンダ(銀色ベース+ブラックカウンター)
- 機能:曜日・日付・月表示+月齢+クロノグラフ
- ムーブメント:El Primero 3610 自動巻き(36,000 vph、60時間パワーリザーブ)
- 防水:50m
- 公定価格:¥116,600 → 約259万円
💬 「これは“曜日を知るための時計”ではなく、“時間を味わうための装置”」
■ 編集部コメント:曜日表示は“便利”か“無駄”か?
「スマートフォンが常時接続された現代において、曜日表示は“不要”だと主張する声もある。
だが逆に——
- 腕時計を見るだけで週の進捗が把握できる
- 会議・出張・休日の予定を視覚的に整理できる
というアナログならではの利便性もまた事実だ。
2026年、曜日表示は単なる機能ではなく、
“自分の時間の使い方”に対する意識の表れかもしれない。」
- 2026年01月23日(金)17時20分
ベル&ロス、日本限定99本モデル「BR-05 RED BLACK CERAMIC」発売~
BR-05 RED BLACK CERAMIC~BR-05 レッド ブラック セラミック 日本限定モデル
大胆なレッドダイヤルと、洗練された煌めきを放つブラックセラミックケースが強烈なコントラストを織りなす、BR-05 レッド ブラック セラミックが日本限定99本で登場します。現代的に解釈した大胆なカラーコードを、ベル&ロスのアイコニックなデザイン「四角の中に丸」に取り入れた新しいアーバンタイムピースです。フランスで創業し、スイスで時計製造を行うベル&ロスは、このモダンで大胆なタイムピースを通じて、スーパーコピー時計新しい現代的なスタイルを提示します。
大胆なカラーコードを再解釈する
ベル&ロスにとって、赤色の大胆なカラーコードは特別な意味を持っています。2011年に誕生したBR-05 レッド・レーダーは、航空機のレーダーをモチーフにしたグラフィカルなデザインが特徴で、レーダースクリーンをビームマークがスキャンする様子を見事に再現しました。このコンセプトは、BR-05 レッド・レーダーへと受け継がれ、多くのベル&ロスファンを魅了してきました。このユニークなタイムピースに象徴されるように、ベル&ロスはプロフェッショナルラインにおいて、大胆な赤色のカラーコードが完璧にフィットすることを実証してきました。
本作では、このカラーコードを再解釈し、都会的なデザインに取り入れることで、新たなスタイルへと昇華させました。ポリッシュとヘアラインの繊細な仕上げ分けを施したブラックセラミックケースに、サンレイ仕上げのレッドダイヤルを組み合わせることで、強烈なコントラストを創出しました。ベル&ロスのクリエイティビティによって、大胆なカラーコードはアーバンデザインのブラックセラミックケースと完璧に融合しています。
モダンで都会的な輝き
ベル&ロスにとって、視認性の確保は不可欠な条件です。時分針およびインデックスには、オレンジに発光するスーパールミノバを採用し、暗所においても優れた視認性を実現しています。立体的なダイヤルリングとシャープなバーインデックスによって構成されたダイヤルは、1分ごとのミニッツマーカーを排したことで、ミニマルなデザインに仕上がっています。41mmのブラックセラミックケース内には、約54時間のパワーリザーブを備えた自動巻きキャリバーBR-CAL.321-1を搭載しています。
【仕様】
BR-05 レッド ブラック セラミック 日本限定モデル
BR-05 RED BLACK CERAMIC
Ref.BR05A-RED-BL-CE/SCE
税込価格:1,177,000
限定:99本
ムーブメント : キャリバー BR-CAL.321-1(自動巻き)
・パワーリザーブ54時間。
・機能 : 時、分、秒、日付。
ケース :ポリッシュ/サテン仕上げブラック セラミック
・ケースサイズ:41mm
・ねじ込み式リューズ
・リューズガード。
・サファイアクリスタル ケースバック
・カバーガラス: 反射防止サファイアクリスタル
・防水性:100m
文字盤:レッド
・サンレイ仕上げ。
ブレスレット: ポリッシュ/サテン仕上げブラック セラミック
・バックル :ス テンレススティール製フォールディングバ ックル
【お問い合わせ】
ベル&ロス 銀座ブティック
〒104-0061 東京都中央区銀座4-9-13
Tel. 03-6264-3989
#bellross
[ベル&ロス]
ベル&ロスの歴史は1994年、二人の親友、カルロス・ロシロとブルーノ・ベラミッシュの時計製造と航空への情熱によって切り開かれました。フランスとスイスのヘリテージを持つベル&ロスは、一躍、本格アビエーションウォッチの分野で代表的な存在となりました。
2005年には、航空計器からインスピレーションを得て誕生したBR-01を通じて、革新的なデザインコードを生み出し、その“四角の中に丸”という象徴的なデザインは、全ての基幹コレクション、プロフェッショナルに向けたBR-03、都会的なBR-05、前衛的なBR-X5に受け継がれています。革新性と卓越性のシナジーによって体現される“コックピットから腕時計へ”という思想は、極限のプロフェッショナルだけでなく、機能的で独創的な時計を求めるあらゆる人々に向けられています。現在ベル&ロスは、600の販売店、25の高級ブティックからなる、厳選された国際的ネットワークを通じて、80か国以上に拠点を置いています。また、その世界は、パトルイユ・ド・フランス及びRafale Solo Displayとの権威的なパートナーシップによって結ばれています。
- 2025年12月16日(火)11時22分
オメガによると、この新機構により日差0〜+2秒の精度を実現したとのことだ。
最終的には、オメガはスピレート™システムを量産化し、他モデルにも横展開する計画だ。
一介の時計ライターで時計師ではない私は、HODINKEEのテクニカルマネージャー、職場では“主任時計師”と呼ぶトラヴィス・ハインズに電話をかけ、新しいスピレート™システムを理解する手助けをしてもらうことにした。この新技術がなぜこれほどまでにエキサイティングなのかを理解するために、まず時計の精度を調整するとはどういうことか、そして従来の調整方法を理解した上で、スピレート™システムがどのようにそれを改善したかに迫った。
まず、時計を調整するとは何を意味するのだろうか?
スーパーコピー 代引き「時計の精度調整とは、簡単に言えばテンプの往復運動の振動数を変えることです」とハインズは説明する。これにはヒゲゼンマイの“有効長”を変えるのが一般的で、ヒゲゼンマイに取り付けられたテンプがヒゲゼンマイの弾性力で反対方向に引っ張られる前にどれだけ回転できるかを変えるのである。「ヒゲゼンマイの長さを調節することで、時計の振動を早くしたり、遅くしたりすることができます」。
現在、時計の調速機構には一般的にふたつの方式が採用される。
伝統的な緩急針で調速するノモスのキャリバー。
「まず一般的に見られる調整方法は、緩急針を使用する方法です」とトラヴィスは言う。「これは現在でも業界で広く使われています。ヒゲ受けとヒゲ棒からなる2本の調整ピンでヒゲゼンマイを挟み、それらが取り付けられた緩急針のアームを上下に動かすことで、ヒゲゼンマイの全長を短くしたり長くしたりします。伝統的に、これが時計の精度を調整する最も簡便な方法です」
マイクロステラ・ナットを備えたロレックスのテンプ。
もうひとつの一般的な調整方法は、ロレックスのマイクロステラ機構やパテックのジャイロマックスに代表されるフリースプリング方式である。これはヒゲゼンマイに緩急針が介入(接触)しないことを意味する。「その代わりに、テンワ自体に取り付けられた錘(おもり)や偏心ネジによって緩急を調節しています」とハインズは言う。「テンワに取付けられた偏心錘は、フィギュアスケート選手のようなものだと考えてください。フィギュアスケーターは、腕を引き込むとスピードが上がり、腕を出すとスピードが落ちますよね? それと同じことを、テンワにある小さなネジが実行しているのです。テンワの輪の中心に向かって重心をかけると、スピードが上がり、時間が早く進みます。反対にその錘の重心を外側に向けると、スピードが遅くなるというわけです」
なるほど。だけど、それとオメガに何の関係がある? 彼らはどんなテンプを採用しているのか?
標準的なオメガのSi14ヒゲゼンマイ。
オメガは2008年にSi14シリコン製ヒゲゼンマイを発表した。他のメーカーも、ニヴァロックスなどの従来の合金に比べて耐磁性や耐熱性に優れているシリコンを採用するようになった。それ以来、オメガはヒゲゼンマイの調速にフリースプラング方式を採用してきた。しかし、これがなかなか難題なのだ。
「この方式の最大の難題は、重心を変えるときに超精密な作業を要求されることです」と、ハインズは言う。「1mmでも誤差が生じると、片方の錘が重くなってしまうため、調速に悪影響を与えることになります。新しいスピレート™システムは、私の見立てではテンプは工場出荷時に固定され、調整そのものはヒゲゼンマイ調整システムで実施することになるのではないでしょうか」
スピレート™システムは、ヒゲゼンマイに柔軟な“ブレード(刃状の部品)”を取り付けることで機能し、ヒゲゼンマイの剛性に影響を与えるよう簡単に調整することが可能だ。
スピレート™システムでは、ヒゲゼンマイ(オメガのロゴの下にある薄い部品)に柔軟なブレードが与えられた。このブレードはヒゲゼンマイに取り付けられ、その長い“尾”がテンプ受けに取り付けられ、そこで調整することが可能だ。
スピレート™システムは、オメガの標準的なシリコン製ヒゲゼンマイに柔軟なブレードを取り付け、そこから長い“尾”を伸ばしてテンプ受けに取り付けられている。この取り付け部分は、スネイルカム(下の画像ではネジのように見える)で調整することが可能だ。このブレードはヒゲゼンマイに接続されており、ヒゲゼンマイの剛性を調整する役割を担っている。
その仕組みの詳細をご紹介しよう。
スピレート™システムは、上図の赤で囲った部分を指す。赤と緑の矢印は、ヒゲゼンマイに作用するブレードの向きを指している。このブレードの底に、ふたつの部品が取り付けられているのがわかるだろうか。ひとつ目の太い部品がヒゲゼンマイだ。ふたつ目の細い“尾”はカーブして調速機(「+/-」が刻印されている)に取り付けられ、さらにカーブしてテンプ受け(「0.1s/d」と刻印されたスネイルカムの下)に取り付けられている。
ハインズによると、調速アームとスネイルカムがヒゲゼンマイの調節を可能にしているとのことだ。調速アームは直接調整することで大きな調整ができ、スネイルカムはオメガがうたう10分の1秒単位の微調整を可能にし、全体として日差0〜+2秒までの調節を可能にしているそうだ。スピレート™システムの“尾”の取り付け位置をテンプ受けで調整すると、“尾”部分が柔軟なブレードを押したり引いたりすることで、弾性を強めたり弱めたりすることが可能だ。ブレードはヒゲゼンマイに取り付けられているため、ヒゲゼンマイに作用する。例えば、“尾”の取り付け位置を近づけてブレードを押すと、ブレードの張力が高まり、ヒゲゼンマイの剛性が上がることで振動が速くなる。
このように、スネイルカムは、時計師が従来の調整方法を用いて手作業で再現することが不可能なほど細かい調整を可能にする。カムの外側にある目盛りは、単に見映えのためだけでなく、調整の目安にするためのガイドだ。
「私は新しいイノベーションを見るのが好きなので、この部分にとても興奮しますね。オメガは本質的に、テンワの偏心錘の重心を変えたり、緩急針を使ったりする代わりに、ヒゲゼンマイ自体の硬さを調整する、第3の調速機構を発明したことになります。つまり、ゼンマイが硬くなれば、テンワは速く振動し、柔らかくなれば遅く振動するということです」
スピレート™システムは、オメガとその顧客の双方にとって、オメガの現在のムーブメント調整法に対する改善を意味する。
ハインズによると、テンプの重心を調整して時計を調整する現在の方法は、オメガにとって悩みの種であるという。時計の精度の誤差が大きいことは、顧客からの最も多いクレームにつながるだけでなく、テンワ上の偏心錘をいじって調整するのは手間がかかることなのだ。また、きちんと調整しようと思えば大型の器具が必要となり、ヒゲゼンマイを誤って割ってしまうと、テンプごと交換しなければならないという問題もある。
「ブティックにとっては、誤って壊してしまう可能性のある部品から調整位置を離すことができるので、この方がはるかに有利だと思います」。オメガはスピレート™によって、時計自体(特にヒゲゼンマイ)へのリスクを最小限に抑えながら、ブティックで訓練すれば誰でも精度が出せるほど調整と調節を簡単にしたのだ。
オメガのスピレート™システムは、機械式時計製造の精度の分野に大きな飛躍をもたらすだろう。
オメガは、新モデルのスピードマスター スーパーレーシングにスピレート™システムを導入したが、製造プロセスを量産化し、最終的には同社のムーブメント全体に展開する予定だと表明している。オメガがこれを実現し、システムが期待どおりに機能すれば、計時技術にとって大きな飛躍になるだろうとハインズは期待する。
ハインズは、20世紀初頭にメーカーがスティール製から温度や磁気に強いニヴァロックス合金製のヒゲゼンマイに移行したことと比較して、「これは、従来のブルースティール製ヒゲゼンマイから温度変化や磁気の耐性がより高いニヴァロックス製ヒゲゼンマイへの移行に匹敵する技術革新だといえるでしょう」と述べている。「それによって精度や磁気対策が飛躍的に向上しました。2008年にオメガがニヴァロックス合金のヒゲゼンマイをシリコン製に変更したことよりも、このスピレート™システムは大きな飛躍であるといえます」
「まったくもって素晴らしい発明だと思います。この点は、いくら強調してもしきれません。劇的な変化がない分野に、まったく新しい方式を追加するイノベーションが目の当たりにするなんて、とてもエキサイティングなことだと思います」
ライバルたちよ、どう対抗する?
さて、精度の話題も忘れてはいけない。2014年以降、オメガはマスタークロノメーター認定を全モデルに展開している。マスタークロノメーターの認定を取得するには、オメガのムーブメントはCOSCの認定を受け、ケーシング後、主に耐磁性と精度に焦点を当てたMETASの8つのテストを受ける。ロレックスの“スパーレイティヴ・クロノメーター(Superlative Chronometer)”認定は、日差-2〜+2秒の精度を誇る(ロレックスのクロノメーター試験については、ロレックス社内に招かれたジェームズが、詳しく取材してくれている)。スピレート™システムは、オメガの精度認定を1歩進め、日差0〜+2秒の精度を約束している。
「この発表により、精度の点で競争しようとするブランド、ロレックスやゼニスが思い浮かびますが、彼らは、すでにスピレート™システムに似たもので追随する方法を模索していることでしょう」と、ハインズは語っている。
- 2025年12月06日(土)15時22分
グランドセイコーは、この新しいSBGJ271、通称 “雪化床”(ゆきげしょう)を新しいバリエーションとして追加した。
グランドセイコーは、ハイビートキャリバーを搭載するエレガンスコレクションのGMTモデルに、この新しいSBGJ271、通称 “雪化床”(ゆきげしょう)を新しいバリエーションとして追加した。この時計は、グランドセイコーのトラベル志向のデザイン精神をすべて受け継ぎながら、白い質感のある表面がダイヤルを覆い、冬の寒さを表現している。
Grand Seiko SBGJ27 Yukigesho
そこで登場するのがこの雪化床だ。雪化粧といえば化粧したように雪で美しくおおわれることだが、漆塗りの光沢のある床に木々に積もる雪の風景を映した様子から名づけられている。
それもそのはず、スーパーコピー 代金引換優良サイト今回のモデルは新ダイヤル以外、エレガンスコレクションの他のハイビートGMTと異なる点は本当に何もないのだ。では、それについてお話しよう。この模様自体は、SBGH269で初めて登場したもので、そのときは赤のカラーリング。美的観点から、その時計は秋の紅葉を連想させるもので、印象的な赤が目立つダイヤルパターンだった。
Grand Seiko SBGJ27 Yukigesho
SBGJ271では、細かい模様や文字盤の細工はそのままに、フラットホワイトを用いることで、全体の表現がより淡く、雪が舞う季節のような少し柔らかく感じられるようになっている。雪が積もったダイヤルの下には55時間のパワーリザーブと日差±3秒という驚異的な精度を誇るハイビートGMTCal.9S86を搭載。その名の通り、3万6000振動/時のハイビートムーブメントで、よりスムースな運針を実現した。
また、サテン仕上げとポリッシュ仕上げのスティール製ブレスレットには、GSのロゴが入ったプッシュボタン式のディプロワイヤントクラスプが付属しており、この時計の落ち着いた雪のような美しさをさらに引き立てている。このSBGJ271雪化粧は3月10日発売。価格は91万3000円(税込)だ。
我々の考え
グランドセイコーは、時計の文字盤の作り方を知っている。他のどのブランドよりも、既存のモデルの文字盤が光り輝くのは、文字盤の出来がよいからこそだ。このモデルを実機で見ていないため、同社のほかのモデルでの経験からしかお伝えすることはできないだが、その経験からこの文字盤は非常に美しく、長いあいだスノーフレークに魅了されながら、もっと旅に出たいと願っていたGMTにこだわるこのグランドセイコーファンも満足するはずだろう。
そう、確かにこれはスノーフレークと同じダイヤルデザインではないが、似たような雰囲気を醸し出している。雪の結晶のような雰囲気なのだ。そして正直なところ、文字通りひとはけの雪からインスピレーションを受けたもので、私にとっては十分な接点だといえる。文字盤の縦のラインは、木に通じるものがあって好きだ。SBGH269で秋という季節を連想させたが、この時計でも同じ。しかし、文字盤のパターンは共通でも、時計そのものは(少なくともグランドセイコーの基準では)ほとんどすべての点で大きく異なっているのである。
Grand Seiko SBGJ27 Yukigesho
まず、秋をテーマにしたこのモデルは、GMTではなく、よりシンプルなタイム&デイト表示となっている。そのため、赤の色調を際立たせ、視認性を妨げないようにしていた。雪化粧ではGMT機構や24時間針の追加によって、より込み入ったダイヤルレイアウトが採用されているため、ホワイトダイヤルは調和のとれたデザインを可能にしている。
この作品をよく見ると、垂直性に加えて、風に舞うような雪を連想させる、ほとんど渦を巻くようなモチーフがあることがわかるだろう。雪の粉のような...いや、もういい、雪はやめよう。さらによく見ると、数字や文字盤の文字が白い面の上に浮かび上がっているように見える。グランドセイコーがメカだけでなく、文字盤の細部にもこだわっていることが伝わる。もちろん、この時計はハイビートなだけでなく、単独で操作できる時針と日付の前後操作を可能とするフライヤーGMTを搭載。
Grand Seiko SBGJ27 Yukigesho
グランドセイコーの文字盤は、常に新しいものが発表されるため、ついつい見過ごしてしまいがちだ。でも、たまに、これだ! という時計が現れる。これは、形と機能の両方の観点から私にとってそのひとつであり、私は近いうちにこの時計を実際に手に取って見ることができるかもしれないと楽しみにしている。
基本情報
ブランド: グランドセイコー(Grand Seiko)
モデル名: 雪化床(Yukigesho)
型番: SBGJ27
直径: 39.5mm
厚さ: 14.4mm
ケース素材: ステンレススティール
文字盤色: ホワイト
インデックス: アプライドとアラビア数字
夜光: なし
防水性能: 30m
ストラップ/ブレスレット: ブレスレット
Grand Seiko SBGJ27 Yukigesho
ムーブメント情報
キャリバー: ハイビートGMT Cal.9S86
機能: 時、分、秒、日付、GMT
パワーリザーブ: 55時間
巻き上げ方式: 自動巻き
振動数: 3万6000振動/時
クロノメーター認定: なし
価格 & 発売時期
価格: 91万3000円(税込)
- 2025年12月06日(土)15時19分
Louis Erard 「2340」~全てが新しいスポーティシックなコレクション「2340」を発表
ルイ・エラールは、全てが新しいスポーツコレクション「2340」を2025 年10 月下旬より、全国の正規時計専門店と直営店にて発売致します。デザイン、ディテール、クオリティが凝縮されたブランド初のインテグレーテッド・ブレスレット モデル。
スチールとチタンのコンビネーション。考え尽くされたデザインと構造、ディテールとクオリティを追求した本コレクション「2340」は、メティエダールやコラボレーション コレクションに続くもので、ルイ・エラールの新たな進化を示唆します。新たな戦略の始動から5 年。ついにブランド初となる、インテグレーテッド・ブレスレット(ケース一体型ブレスレット)搭載モデルの登場です。
新コレクション「2340」は、ロレックス時計コピー代引き 優良サイトブランドの拠点であるスイス・ノワールモンの郵便番号であり、Louis Erard にとって新たな章を象徴する数字です。
新しいブレスレット、新しいケース、そしてコレクション初のムーブメントを搭載します。
技術・美観ともに、すべてのディテールは「執念」によって磨き上げられました。限定品ではなく、ブランドの未来を担う基盤となるモデル。スポーティシックをルイ・エラール流に再解釈した新コレクションの幕開けです。
CEO のマニュエル・エムシュは次のように語ります。
「インテグレーテッド・ブレスレットをデザインする時が来たのです。2 年の開発を経て完成した美しいブレスレットは、チタンとスチールを融合させ、バックル部分に向け緩やかな細みを持たせたテーパード・デザイン。ブラッシュ仕上げとポリッシュ仕上げのコントラスト。そして、組み上げた後に1 コマずつ面取りを施す、完璧で繊細な工程を要します。どのパーツも極めて緻密でありながら、全体は流れるように調和しています。この仕上げレベルは、いわゆる“ハイ・オロロジー”に匹敵しますが、その価格ではありません。時計製造の精通者なら、その違いを“感じる”はずです。これはデザインを超えた、エンジニアリングそのもの。精緻なケースと深みあるダイヤル。
これこそ、私たちのスポーツウォッチの設計図です。5 年の進化を、この1 本に凝縮しました。そして、これは始まりにすぎません。」
新しいスポーツコレクション「2340」
単なる新作時計ではなく、ブランドの節目を刻む存在となるコレクション。
「レギュレーターやコラボレーションの先にある、Louis Erard の次なる一歩は?」という、その問いへの答えが、この2340。スポーティシックの世界に、私たち自身の言葉で踏み出します。
1929 年から変わらぬデザインへの執念とディテールへのこだわりが、これまで以上に「2340」には息づいています。
≪主な特徴≫
初のインテグレーテッド・ブレスレット~ブレスレット構成部品数:92
ブランドの意思を体現するデザイン
Louis Erard 独自の解釈で具現化した2340 のブレスレットは、力強いデザインステートメントです。
5 連テーパード構造で、92 個のパーツ(リンク46 個、エンドリンク2 個、ピン32 本、スクリュー12 本)から構成されます。
ブラッシュ仕上げのチタンとポリッシュ仕上げのスチールのコントラストが、奥行きと洗練を演出します。各リンクは組み立て後に職人が手作業で面取りし、完璧な仕上げを追求。バタフライクラスプは完全に隠れる仕様で、装着時のラインを途切れさせません。ケースから自然に流れ出すような視覚的連続性と構造的統一感を実現しています。これは偉大なインテグレーテッドデザインへのオマージュであり、Louis Erard 独自の言語で再解釈されたものです。
チタン&スチール製/5 連テーパード構造/中央リンクはポリッシュ仕上げスチール/外側リンクはブラッシュ仕上げチタン/スプリングブレード式バタフライクラスプ。
ハイブリッドケース
ミドルケースは軽量なブラッシュ仕上げチタン。ラグ、ベゼル、リューズ、ケースバックはポリッシュ仕上げのステンレススチール。
新ムーブメント「Sellita SW300-1」(Louis Erard 初採用)
ムーブメントには厚さ3.6mm のスイス製自動巻きキャリバー Sellita SW300-1 を搭載。
本モデルがブランド初の採用となります。ブラックラッカー仕上げの特製ローターには、Louis Erard のサインと独自の装飾を施しています。
3つの表情を持つ3種類のダイヤル
・ミントグリーン[ピル(カプセル)パターン/6 時位置にカプセルロゴ]
・スレートブルー(ブレスレットのセンターリンクから着想を得たリニアテクスチャー)
・ディープブルー(ブレスレットのセンターリンクから着想を得たリニアテクスチャー)
それぞれ異なるスタンピング技術により、立体感と深みを演出。
浮遊感のあるダイヤモンドカットのインデックスと、ブラッシュ&ポリッシュ仕上げの針が光を捉えます。
ダイヤル外周にはレイルウェイトラックを配し、Louis Erard のロゴをさりげなく組み込みました。
限定生産ではなく、コアコレクションの一部として展開
フルスチールモデル比で30%軽量
デザインの核となるケース
ケースサイズは直径40mm(ラグ to ラグ 41.5mm)、スリムで装着感に優れたプロポーション。
ミドルケースは軽量なブラッシュ仕上げチタン。ラグ・ベゼル・リューズ・ケースバックはポリッシュ仕上げのステンレススチールでコントラストを強調。両サイドに配された4 本のポリッシュ仕上げのガドゥルーンが、2340 のアイデンティティを際立たせるとともに、ブレスレット接合部を巧みに隠しています。
2 つの明確なコンセプトをデザインアイデンティティを持つコレクション構成
ノワールモン コレクション:1992 年以来の本拠地の名を冠し、コラボレーションとメティエダールにより高級複雑時計技術を追求するコレクション。
2340 コレクション:ブランド本拠地であるノワールモンの郵便番号から名を得た、新たな素材・パートナーシップ・スポーティシックの未来を象徴するコレクション。
スポーティシックなこのコレクション「2340」は、全国の厳選された時計専門店と直営店にて、まず3色のダイアルバージョンで発売されます。日本円価格は759,000 円(税込)です。
【仕様】
コレクション「2340」
価格: 各 759,000 円(税込)
ルイ・エラール 2340 ミント
品番: LE35123TA11.BMT12
ダイアル: ミントグリーン ラッカー仕上げ - オブロング(ピル)型スタンプパターン
ルイ・エラール 2340 スレート
品番:LE35123TA02.BMT12
ダイアル: スレートブルー ラッカー仕上げ ‒ ホリゾンタル ウェーブパターン
ルイ・エラール 2340 ブルー
品番:LE35123TA01.BMT12
ダイアル: ディープブルー ラッカー仕上げ ‒ ホリゾンタル ウェーブパターン
(共通)
ムーブメント:Sellita SW300-1 (自動巻)
・3 針
・ムーブメントサイズ:直径25.60 mm/厚さ:3.60 mm
・25 石
・振動数:28,800振動/時(4 Hz)
・特製オープンワーク・ローター(ブラックラッカー仕上げ、Louis Erard シンボル入り)
・パワーリザーブ:約56 時間
・機能: 中央時針・分針・秒針(HMS)
ケース: サテン仕上げチタンおよびポリッシュ仕上げステンレススチール
・ケースサイズ:径40 mm/厚 8.95 mm
・ラグ to ラグ:41.50 mm
・3 ピース構造
・両面反射防止加工サファイアクリスタル
・ステンレススチール製スクリューバック(クローズド)
・防水性能:5 気圧(50 m/165 ft)
ダイアル: ブラック転写のレイルウェイトラック
・3 時位置に「LE」ロゴ入りサテンプレート
・ロジウムメッキのダイヤモンドカットインデックス
・SLN-C1(ブルー発光)夜光塗料
・針: ロジウムメッキ、サテン仕上げトップ/ダイヤモンドカットエッジ、SLN-C1(ブルー)夜光塗料
ブレスレット: サテン仕上げチタンおよびポリッシュ仕上げステンレススチール
・バタフライフォールディングクラスプ(スプリングブレード機構)
【お問い合わせ】
大沢商会
TEL: 03-3527-2682
[LOUIS ERARD(ルイ・エラール)]
時計製造の聖地であるジュラ山脈に拠点を置くルイ エラール(Louis Erard)は、1929 年にルイ・エラール氏により設立され、スイスの機械式技術と伝統を大切に体現するブランドです。ルイ・エラールは、ラグジュアリー、永遠性、そしてエレガンスを融合した機械式時計コレクションを展開し、象徴的なレギュレーターで知られています。今日、マニュエル・エムシュのリーダーシップのもと、ブランドの歴史や時計製造の伝統を継承、尊重し、現代的に再解釈しながら進化しています。メティエダール(伝統工芸)をモダンに昇華し、また、様々な分野とのコラボレーションやノウハウの交流を通じて表現の領域を広げています。ルイ・エラールは、大衆向けのブランドとは異なる、コレクタブルな道を歩み続けており、高級時計製造にインスパイアを受けながら、独自のポジションを築いていきます。
- 2025年11月21日(金)12時49分
1位指名で名前を呼ばれるときにこの時計をつけているかもしれないと、密かに楽しみにしていた。
記録的な視聴率を記録した女子NCAAトーナメントが閉幕したばかりだが、すでに皆はそれから間もない15日夜に開催されたWNBAドラフトに注目していた。アイオワ・ホークアイズに属する天才、有名人であり、タグホイヤーコピーN級 代引きそしてスーパースターのケイトリン・クラーク(Caitlin Clark)が、現在インディアナ・フィーバーが保持しているドラフト1位指名を受けると熱い予想がなされていたのだ。彼女は今シーズンで記録的な活躍を見せ、女子バスケットボール界を一気に飛躍させた。彼女はつい先週末は『サタデー・ナイト・ライブ(Saturday Night Live, SNL)』に出演し、先月にはアイス・キューブ(Ice Cube)からビッグスリーリーグでのプレーオファーを受けている。今世間の関心は、クラークを筆頭とした女子リーグへと向けられている。
WNBA
しかしまさか、その人気の高まりが、私の大好きな時計の世界とクロスオーバーするとは思ってもみなかった。そして私が時計と同じくらい夢中になっている唯一のスポーツがバスケットボールであることを考えると、ティソの最新作にも俄然興味が湧いてくる。今回、このブランドは3社によるコラボレーションモデルを発表した。1社目がティソ、次がウィルソン(バスケットボールの製造元ブランドだ)、そして最後がWNBAだ。これは、史上初のWNBAオフィシャルウォッチとなる。ティソはすでにNBAの公式スポンサーであり、今作は理論上、そのパートナーシップの延長線上にあると考えられる。
このシースターは2モデルあるが、ここではティソのパワーマティック 80 ムーブメントを搭載した自動巻きモデルを取り上げる。私たちを待ち構えていたのは、本当に特別なアイテムのように感じられる、思いの詰まったコラボレーションだった。まずは色について。ブラックの文字盤とベゼルに、バスケットボールをオマージュしたオレンジのアクセントが効いている。しかし、ベゼルは通常のダイブタイム表示ではなく、よく見ると“24”の数字があることに気づくだろう。いや、これはデイトナ24時間レースへのオマージュではなく、ショットクロック(チームはボールをコントロールしてから24秒以内にシュートを打たなければならないというルール)の長さを表しているのだ。
Tissot
この時計には、白とオレンジの配色でWNBAバスケットボールの特徴的な色と質感を表現した、ウィルソンによる2本のストラップが用意されている。すなわちこの時計には、それぞれウィルソンとWNBAのロゴが入ったオレンジとホワイトのストラップが両方付属することになる。
時計を裏返すと、80時間のパワーリザーブにニヴァクロン製のヒゲゼンマイを備えたパワーマティック 80 ムーブメントが見える。しかしケースバックにはバスケットボールのエッチングが施されているので、ちょっと見にくいと感じるかもしれない。
Tissot
WNBAと女子リーグが勢いを増してきているのは明らかだ。このようなリリースが、いままさに成長している競技の熱を継続させるのに貢献しているのだと私は思う。ケイトリン・クラークやその他の選手がこの最新コラボアイテムをドラフトの場で着用したにせよしなかったにせよ、昨晩はそれを確かめるために私を含めた多くの人々の関心を集めたことだろう。
ティソ ティソ シースター ウィルソン WNBA パワーマティック 80。直径40mm x 厚さ12.5mm。ショットクロックベゼル、WNBAウィルソン®︎バスケットボール シースルーケースバック。ブラックダイヤル、ニヴァクロン™️製ヒゲゼンマイを備えたパワーマティック 80 ムーブメント。交換が簡単なクイックリリースを備えた2本のWilson WNBA Evo-NXT プレミアム コンポジット ゲームボール素材ストラップ。価格: 11万円(税込)。日本では5月発売予定。本稿は本国版の翻訳です。
- 2025年08月30日(土)11時49分
パテック フィリップ アクアノート 5164G 、アクアノートはその王者だと思っている。
Ref.5164Aのディスコンについて書いたとき、私はそれを“愛好家に人気”と呼んだ。4万ドル(日本円で約618万円)以上もして、パテックのVIP以外はほとんど手に入らなかった時計に対して少し言いすぎかもしれないが、つけているのを想像するだけで素晴らしく、幸運にも本当に所有することができればさらに素晴らしい時計であるのは確かだ。クールなデザイン、快適なストラップ、スポーティな仕様(防水性からスティールケースまで)、黒のカラーリングなど、すべてが“クワイエットラグジュアリー”が流行する以前からクワイエットラグジュアリーの最高峰だった。
アクアノート・トラベルタイムにはエレガントさがあり、パテック フィリップスーパーコピーN級 代引きそれは新しいRef.5164Gでも変わらない。私は旅行に行くとき必ずと言っていいほどロレックスのGMTマスターIIを使っているが、ケースの左側にあるプッシャーを使用する触感の魅力は格別である。新しいタイムゾーンを設定するには“フライヤー”GMTを使うのが比較的簡単だが(リューズを緩めて適当な位置まで引き出し、時を進めるか戻す)、5164のプッシャーを使用する感覚に匹敵するものはない。上のプッシャーはクリックごとに時針を1時間進め、下のプッシャーは時を戻す。いずれにせよスケルトナイズさせた時針で目立たせないようにしつつ、ホームタイムを指し示し続ける。またふたつの開口部はホームタイムとローカルタイムゾーンの昼夜を追跡(青が夜、白が昼)し、6時位置のインダイヤルでは日付を表示するなど、これは左右対称の美しい時計である。
このタイプのデザインはパテックにおいて長い歴史があり、1960年代初頭のカラトラバ・トラベルタイム Ref.2597にまでさかのぼる。ジェームズ・ステイシーが2019年に執筆した5164RのHands-On記事で述べていたように、2597のムーブメントは、ワールドタイム機能の父と呼ばれるルイ・コティエ(Louis Cottier)の発想から生まれたものである。つまりRef.5164は、創造性という重要な系譜を受け継いでいると言える。しかし、アクアノート・トラベルタイムの大胆なデザインとスポーティさは、おそらくコティエが想像していたものをはるかに超えている。
Ref.5164Aはもう入手できないが、パテックがこのロングランリファレンスを貴金属製の新バージョンで継続することは、ある程度予想できた。ただ私はパテックが新しいアクアノート・トラベルタイムを発表して、それをSS製の新リファレンスで提供してくれることを望んでいた。もしそれが発表されていたら、今年のように閑散としたWatches & Wondersでは最大のリリースとなる可能性が高かった。ただ、いまのところSS製のスポーツモデルを避けるというブランドの決定に沿ったものではなかっただろう。
またアクアノート・トラベルタイムのRef.5164がローズゴールド製でカタログに残っているため、2世代の時計がカタログに同時に掲載されることは考えにくかった。新しく再導入されたホワイトゴールドバージョンは(RGと)同じCal.26-330 S C FUSムーブメントを採用しているため、主にケース素材と文字盤/ストラップの色が変更されただけである。しかし手首への装着感も変わってくる。
アクアノート・トラベルタイムは、市場で最もつけ心地のいいスポーツウォッチのひとつであり、素晴らしいカスタムカットのラバーストラップとデプロイヤントクラスプを備える。ケースの厚さは10.2mmとスリムで、2時から8時までの対角線幅は40.8mmである。また、ラグは手首を包み込むように下がっている。しかしゴールドにすると、時計の上部が重く感じられるようになる。これはブレスレットではなく、ストラップを採用した貴金属製スポーツウォッチの多くが抱える問題であり、重いケース素材がバランスを崩してしまうのだ。またパテックは防水性を5164Aの120mから30mに低下させるというより実用的な方法で、この時計のスポーティさを減らした。どちらの金無垢モデルにもシースルーバックが採用されていたが、残念なことに新しい防水性能はアクアノートを水中に持っていくことを少し躊躇させる仕様となった。
しかし、フィット感やバランスの問題は、新しい文字盤の色と同様に個人の好みである。ロレックスは顧客の好みに合わせて色の選択肢を提供する傾向があるが、パテックはそのような道を選んでいない。彼らは使用する素材に対する自信(顧客の需要を無視してでも)、強いデザインセンスを持っている。何年か静かなリリースが続いたあと、パテックは“カーキ”のアクアノート・トラベルタイムを、WGやもっと大胆なプラチナ製でリリースして、“話題の波”を生み出したかったのではないかと想像していた。しかしパテックが引き続き需要を抑えようとしていることには、おそらく何か意味があるのだろう。5164Aの価格は、小売価格までとはいかないが徐々に下がってきている。
代わりにオパラインブルーグレーの文字盤、アクアノート・エンボス・パターン、WG製ケース、そして998万円(税込)の値札がついたモデルを得た。写真で見た限りでは、ダイヤルがライトブルーすぎて、私のような控えめなものが好きな人には装着できないのではないかと心配だった。長年夢見てきたクラシックな5164Aではないが、実物はより暗く見え、光の加減で変化していた。ということは、幸運にも手に入れることができれば、普段使いとしても活躍できそうだ。
夢のアクアノート・トラベルタイムを手に入れるまでにはもう少しかかりそうだ。これは私が望んでいた時計ではないが、現在手に入るのはこのモデルだ。間違いなく5164Gは、現在13年続いているリファレンスモデル(カタログで最も長命のリファレンスだと思う)として、しばらくは残るだろう。パテックが1年後に新モデルを発表するためだけに、まったく新たなモデルを投入するとは考えにくい。そのあいだ、多くの人々が新しい5164Gを楽しむことになるだろう。ジェームズの言葉を借りれば、これは私が選ぶ最もクールな現代のパテック フィリップである。SS製アクアノート・トラベルタイムの夢を引き続き持っているが、いま必要なのはこの時計である。パテックが私にとっての聖杯を復活させてくれる日のために、もう少しお金を貯めておこう。
- 2025年08月30日(土)11時47分
再び注目を浴びるバゲットセット仕様の時計たち
バゲットをセットしたスポーツウォッチのトレンドは衰退しつつあるのだろうか? さらに言えば、ミッドセンチュリー期のような生真面目な風潮に回帰しつつあるのだろうか?
彼は世界で最も高級なモダンウォッチ、それもバゲットダイヤモンドをあしらったモデルに大きく予算を割いたのだ。しかし何が彼をジェムセットの時計に傾倒させたのだろうか?
バゲットセット仕様のものは、ジェムセットした時計の頂点に君臨する。それらのなかには趣味のいい華やかなものもあれば、奇抜で退廃的なものもある。ミッドセンチュリーのドレスウォッチに散りばめられたバゲットインデックスには、紛れもなく洗練された雰囲気が漂う。バゲットダイヤモンドは細長く高価であり、ダイヤモンドカットにおけるイングリッド・バーグマン(Ingrid Bergman)のようでもある。全面にバゲットセットを施したスポーツウォッチもあり、こちらもジェムセットの派手さにおいてマグニチュード10相当の破壊力がありそうだ。大胆で隙がなく、やや刺々しさを感じさせる。そう、メイ・ウエスト(Mae West)氏がLAにある中華料理の名店“Mr.Chow”に現れたとき、自然とスタンディングオベーションが起こったような感じだ。
Rexhep Rexhepi
バゲットインデックスを備えたレジェップ・レジェピ クロノメーター コンテンポラン II ディアマン。
現代的なバゲットカットの手法は1912年にカルティエによって編み出された。その後数十年間、アール・デコ期のジュエリーデザイナーたちはクリーンな直線と幾何学的なフォルムを強調するために、このタイプのストーンカットを採用した。バゲットは1930年代のレディースウォッチの装飾にも見られ、男性用の懐中時計および腕時計のダイヤルのインデックス/アワーマーカーにも使用されていた。
Cartier Art Deco timepieces
今日の高級時計製造において、カルティエスーパーコピー時計 代引きバゲットカットは最も好まれるプレシャスストーンのスタイルとなっている。パテックやロレックスのようなスイスの老舗メーカーからジェイコブやMB&Fのような独立系時計メーカーまで、バゲットシェイプの宝石は注目の的だ。スポーツウォッチに最も多く見られるバゲットセット仕様の時計の人気は、(富裕層に限るが)時計収集界隈の上層部において特に顕著だ。宝飾品とは異なり、バゲットをあしらった時計は広大な時計の世界でもほんの一角に過ぎない。希少性や経済的な側面はさておき、バゲットカットの美しさは見る者を驚嘆させる。だから、この記事に掲載されている宝石をあしらった時計の画像をじっくりと眺め、目を眩ませることが心の逃避行となれば幸いである。
バゲットカットの技法を知る
では、なぜバゲットカットがスイスの由緒ある時計ブランドに選ばれるようになったのだろうか。ラウンドストーンと比較するとバゲットは表面積が大きいので、それゆえに好まれるようになったという話もある。「表面積が大きいほど石の視認性と色の輝きが増し、石がより格調高く見えます」。こう解説するのは石のカットとセッティングを専門とし、ジュネーブに本社を置くピエール・サラニトロ(Pierre Salanitro)社である。
Patek
パテック フィリップ アクアノート・ルーチェ Ref.5260/1455R
サラニトロ社はオーデマ ピゲやパテック フィリップを含む高級時計メーカーからジェムセッティングの依頼を受けることが多い。2022年、パテックは同社の株式40%を取得したことを発表。パテックは昨年、ダイヤル、ベゼル、ケースサイド、ブレスレットに130個のバゲットカットのダイヤモンド(8.66ct)と779個のマルチカラーのバゲットカットサファイア(45.05ct)を“インビジブルセッティング”なる技法で取り入れたアクアノート・ルーチェ 《レインボー》ミニットリピーター Ref.5260/1455Rを発表した。なぜって? その答えはパテックのみならず、同業他社にとっても超複雑機構やクラフツマンシップ、そして単に“我々はこれを作ることができる”ということを誇示するのと同列なのかもしれない。
Patek 5719 watch
パテック フィリップ ノーチラス Ref.5719/10G。
ジェムセッティングした時計の消費主義的な側面を非難する前に、宝石のセッティングは尊敬に値する技術であることを理解することは重要だ。「バゲットストーンのセッティングは複雑で、ラウンドストーンのセッティングとは大きく異なります」とサラニトロ社は解説する。「とりわけインビジブルセッティングの技法は石を下から固定し、上から金属素材が見えないようにするため難しいのです」
それを踏まえると高級メーカーがこの技術に傾倒するのは当然だ。アフターマーケットのジェムセッティング業者には完全コピーできないクラフツマンシップを宿す時計……、たとえばロレックスのレインボーデイトナ、パテックのノーチラス Ref. 5719/10Gのようなモデルのリリースはスイスのブランドがアフターマーケットとの差別化を図るための手法のひとつなのだろうか?
Drake wearing a diamond set Nautilus
パテック フィリップのノーチラスRef.5719/10Gを着用するドレイク(Drake)氏。Photo: Getty Images
しかし本当の理由は基本的な経済原理に基づくものなのかもしれない。「スイスにはこの技術を取り扱えるセッター(技師)が非常に少なく、その数は増大し続ける需要を満たすには不十分なのです」とサラニトロ社は説明する。バゲットのセッターにとって課題となるのは、その工程が非常に手間のかかるものであること、そして多くのブランドは単にそのような専門家を揃えるだけの経営資源を持っていないということだ。供給を制限するもうひとつの要因は(これも経済原理だが)、必要な品質の宝石を調達するのが難しいという絶対量の不足の常態化だ。バゲットはほかのカット技法よりもファセットが少ないため、不純物が目立ちやすい。これを避けるにはより質のいい原石が必要だ。つまるところジェムセッティングは、ある匿名の業界関係者が言うところの“職人の飲み比べ合戦”のひとつに過ぎない。これも正統なマーケティング用語のリストに加えようか?
バゲットをアフターマーケットでセッティングすることは可能だが、通常の製造工程で行う技法とは異なる。「セッティングは、たとえばパヴェ(pavé)のようなものではありません。まったく別ものです」。時計ディーラーでありGIA認定宝石鑑定士、4代目宝石商のロイ・ダビドフ(Roy Davidoff)氏は言う。「バゲットをケースにセットするためには時計の構造全体を変える必要があります」。宝石のセッティングを前提としたデザインでない限り、シンメトリー(左右対称性)を実現するのはほとんど不可能に近いのだ。
Gem-set Royal Oak
10本限定のレインボー・ロイヤル オーク Ref.15514BC。ジェムセッティングはサラニトロ社によるもの。バゲットカットのエメラルド861個(~32ct)がセッティングされた、41mm径で自動巻きの18KWG製ロイヤル オーク。
41mm径、自動巻きのWG製ロイヤル オーク、バゲットカットのオレンジスペサルタイトガーネット861個(~47.3ct)。
バゲットカットのピンクトルマリン861個(~35.8カラット)がセッティングされた41mm径の自動巻きロイヤル オーク。
おそらくアフターマーケットでの改造が原因で、宝石がセッティングされた時計は純粋主義者を自認するコレクターや愛好家のあいだで時計学的な逸脱のシンボルとなっている。ジェムセット仕様の時計は往々にして、その美的センスと莫大な値札だけでなく、アイスド・アウト(ド派手な装飾)が施されたアフターマーケットのパヴェケースやプリンセスカットのダイヤモンドがセットされたベゼルを連想させる。時計学の専門家たちによれば、製造時のものから逸脱することはその時計の格を下げる結果にしかならないという。これらは私が支持する考え方ではないが、2024年現在において広く受け入れられている教義なのである。
ハイジュエリーに精通した人々にとってバゲットカットの石は定番であり、これからもそうあり続けるだろう。「私たちが長いバゲットを愛するのは、カットの難しさを知っているからです。ことわざにもあるように“オムレツを作るにはたくさんの卵を割らなければならないし、本当に長いバゲットを作るにはたくさんのダイヤモンドを割らなければならない”のです」。 サザビーズのジュエリー部門、北米担当のフランク・エヴェレット(Frank Everett)副会長はそう説明する。「バゲットの魅力は、タイルのように使えることです。小さなラウンドダイヤモンドでセッティングするのではなく、タイルで敷き詰めるのです。小さなラウンドブリリアントで空間を埋めることは、その隙間を支えの金属で埋めることを意味します。バゲットなら100%ダイヤモンドで空間を埋めることができます。よりラグジュアリー感が増すのです」
VCA Baguette-set jewels
左:ヴァン クリーフ&アーペル “ミステリー・セット”のルビー&ダイヤモンド クリップ ブローチ(1965年ごろ)、右:同じくヴァン クリーフ&アーペルのテーパーバゲットをセットしたイヤリング。 Images: courtesy of Sotheby's
ハイジュエリーにおけるバゲットの使用は、トレンドに左右されるものなのだろうかと私はエヴェレット氏に尋ねた。「バゲットは構成要素です。モチーフを作るのに欠かせない存在だからこそ、使われないということはないでしょう。丸い形状だけではデザインは作れません。直線でなければならないのです」
スポーツウォッチにおけるバゲットセット仕様の台頭
バゲットセット仕様のスポーツウォッチは、ヴァン クリーフ&アーペルのインビジブルセッティングのアールデコ調ブローチとは隔世の感がある。しかしその系譜は、50年代から60年代にかけてパテック フィリップが復活をもたらしたアール・デコのデザインにさかのぼることができる。
パテック フィリップ Ref.3428。Image: courtesy of John Nagayama
女性用カクテルウォッチ以外でも、パテックのカタログを見れば時計デザインにおけるバゲットストーンの使用の進化は明らかである。「バゲットカットのダイヤモンドは比較的軽いため、1930年代から男性用懐中時計や腕時計のダイヤルのインデックスやアワーマーカーとして使われ始め、1950年代から60年代にかけてますます人気が高まりました」と、Collectabilityの共同創設者であるタニア・エドワーズ(Tania Edwards)氏は説明する。そして現代のバゲットセッティングを施したスポーツウォッチの先駆けといえば、パテックのRef.3428だ。ダビドフ氏が“1972年以前のスポーツウォッチ”と表現するRef.2526の後継モデルで、自動巻きムーブメントであるCal.27-460、ボーゲル社製の防水ケース、そしてRef.3428の全体的に堅牢な質感は、パテックが実際にスポーツウォッチを作る前にスポーツウォッチを手がけていたことを物語っている。このRef.3428の究極ともいえる1本は、3時、6時、9時位置にダイヤモンドのバゲットインデックスをあしらっている。
Patek watch
パテック フィリップ Ref.3424/2 。ジルベール・アルベール(Gilbert Albert)デザインによるPt製ケース。 Image: courtesy of Antiquorum
「バゲットダイヤモンドがメンズウォッチのケース装飾に使われるようになったのは、1950年代のことです。1955年にジュエラーのジルベール・アルベールがパテック フィリップに入社すると、時計の装飾に宝石をより実験的に使用するようになりました」。エドワーズ氏はこう解説する。アルベールによるバゲットダイヤモンドの使用は、Ref.3424のように60年代のアシンメトリカルコレクションの大胆で未来的なデザインをさらに際立たせたが、細長いバゲットの使用は伝統的なアール・デコの美学を踏襲していた。
70s baguette-set Patek
パテック フィリップ Ref. 3540とRef.3625。
1970年代を通じて、パテックはRef.3540やRef.3625に代表されるデザイン主導のバゲットセットのモデルをリリースしていた(他社も同様)。これらのデザインは、現代のように洗練されたセッティング技法が一般的になるはるか以前から行われていたものだ。ダビドフ氏は私がWhatsAppで送信した大量の画像に対する返信で次のように述べている。「Ref.3625のセッティングは1本の支えで石を留めるカクテルリングのようなもので、Ref.3540の小さなエメラルドカットはそうですね...…、ベゼル上のふたつの石が正しくセッティングされていませんね。しかしこれは当時許容されていたもので、ロレックスのRef.6270が当時としてはいかによくできていたかを語るのと同じです。クレイジーのひと言です」。ロイ、話題を広げてくれてありがとう。
Rolex ref. 6270
ロレックス デイトナ Ref.6270
ジェムセットされたスポーツウォッチの元祖といえるのがロレックス GMTマスター “SARU” Ref.16758(1980年)だ。厳密にはこの初期ロレックスのジェムセット仕様のリファレンスは、トラピーズカット(Trapeze-Cut)の石を使用している。しかしこれはバゲットと同じ系統のものだ。厳密にバゲットを語るのであれば、Ref.6270(1984年)が真の出発点である。しかし台形型の石は、2000年代初頭のロレックスによるジェムセットしたスポーツモデルの大半に使用されるようになった。まあ、その事実は本記事の進行のために棚上げしておこう。80年代にはケースと同じバケットベゼルを備えたデイデイト、なかでもバゲットのベゼルとセンターリンクを備えたさまざまなオイスタークォーツ “オクトパシー”のバリエーションを含む、ド派手な宝石三昧(ざんまい)のデザインが台頭した。
Rolex Saru
左:ロレックス GMTマスター “SARU” Ref.16758 (1980)。Image: courtesy of The Keystone. 右:ロレックス オイスタークォーツ デイデイト “メカノ” Ref.19168 (1985年)。Image: courtesy of Sotheby's
そして1990年代の自動巻きデイトナの登場後、ロレックスは宝石をちりばめたRef.6270のレシピを取り入れ、スポーツウォッチとジュエリーウォッチの融合、その基準を打ち立てる旅に出た。この試みは、ロレックスによる“プロフェッショナル”向けのツールウォッチメーカーとは真逆のラグジュアリーブランドとなるための多大な努力と相まって絶頂期に達した。ロレックス Ref.16568とその後継モデルはアワーインデックスにバーを配し、そのあいだにふたつのバゲットストーンを敷き詰めたのだった。
ベイエリアを拠点とする時計専門家であり、オンラインオークションプラットフォームLoupe Thisの共同設立者であるエリック・クー(Eric Ku)氏は、「ベゼルのバーは見栄えのためではなく、必要に迫られて使われたのでしょう」と説明する。「専門的なことを言えば、ダイヤルの円周上に石をはめ込むための必要悪だったのです。バーなしでそれを行うと、すべての石を完璧にセットするのは難しいのです。それぞれの石のカラット数にも微小なばらつきがありますし、寸法も微妙に異なります。そうすると欠点が目立つようになります。これはそれを覆い隠す方法のひとつなのでしょうね」
Gem-set Rolex Daytona
ロレックス デイトナ Ref.16568。Image: courtesy of Amsterdam Vintage Watches
2004年、ロレックスはコレクターのあいだで“レオパード”として知られているコスモグラフ デイトナ Ref.116598 SACOをリリースした。ロレックス史上最もエキセントリックな時計といわれるこのモデルは、2012年、そして2018年に登場したデイトナ レインボーのカラフルな先駆けとして登場した(それ以前だと、クー氏が最近販売したという1997年に製造されたユニークピースが存在する)。
Patek ref. 4700-006 ladies' watch
パテック フィリップ ノーチラス Ref.4700/6。Image: courtesy of Christie's
パテック フィリップにおけるバゲットダイヤモンドの最も早い導入は、レディースモデルのノーチラス Ref.4700/6(1984年)とされる。1980年代から1990年代初頭にかけて、パテックは特別注文で紳士用ノーチラスにバゲットダイヤモンドをあしらっていたが、通常生産の紳士用ノーチラスにバゲットダイヤモンドがあしらわれたのは1997年に発表された18KWGまたはPt製Ref.3800/130が初となる。これもまた、明らかなコスト上昇と低需要という事情からごく少量だけ生産されたものだ。
今日においてパテック フィリップはアクアノート・ルーチェを、バゲットセッティングを施した多くの大胆なモデルのキャンバスとして使用している。グレネード柄のダイヤルはこの種のセッティングに適しているが、複雑なジェムセッティングを誇示するためにその主な存在意義である防水性を無視するというのは、まったく表面的な試みに成り下がっていると言えるかもしれない。
Rube Patek Aquanaut watch
ユニークピースの可能性が高いパテック フィリップ アクアノート Ref.5063G (1997年)。 Image: courtesy of Christie's
オーデマ ピゲがロイヤル オークにバゲットを使用し始めたのは1982年のことだ。初の完全アイスド・アウトモデルであるロイヤル オーク Ref.25688は、1989年にユニークピースとして特注された。39mm径のPt製ケースにバゲットカットダイヤモンドが敷き詰められ、MOP(マザー・オブ・パール)のダイヤルにはデイ/デイト表示とムーンフェイズ表示が備わっている。
Ref.25688のような完全なアイスド・アウトモデルは、おそらく仕様変更の結果の産物なのだろう。ダイヤルのシンプルな3・6・9のインデックスから始まり、ベゼルの複雑なセッティング、そしてケース、ブレスレットのセンターリンクへと広がり、最終的には時計全体がバゲットで飾られるようになる。最も極端なケースでは、ムーブメントのブリッジにまで宝石がセッティングされていた。
Omega De Ville Central Tourbillon watch
オメガ デ・ヴィル センタートゥールビヨン 38.7mm Ref.513.98.39.21.56.001
ダビドフ氏はヴァシュロン・コンスタンタンのカリスタ、ピアジェのオーラをアイスド・アウトウォッチの美の先駆者として挙げている。「バゲットの物語は、カリスタなしでは語れません。これは初のフル“バケット”のアイスド・アウトウォッチなのです」と彼は言う。1kgのゴールド無垢のインゴットから削り出され、118個のダイヤモンド(合計130ct)をセッティングしたカリスタ(ギリシャ語で“最も美しい”の意)はカットと組み立てに5年を要した。完成までに費やされた作業時間は実に6000時間を超える。
- 2025年08月25日(月)11時08分
オメガがオリンピックでどのように登場するかを見てみよう。
今年はオリンピックに夢中になった。信じられないような開会式から、よく知られた競技や少し変わった競技まで、ありとあらゆるものを楽しんだ。ストリーミングやほぼリアルタイムのリプレイのおかげで、ありとあらゆることを指先ひとつで見ることができるようになった。もともとオリンピックの大ファンだったが、家で観戦するだけで満足していたため、自分が実際に現地で観ることになるとは思ってもみなかった。今となってはもう一生オリンピックを見逃すなんて考えられない。
Olympics on the Eiffel Tower
“オメガがオリンピックに連れて行ってくれたから、心を奪われたのだろう?”と言われる覚悟はできている。だからこそ、普段この手の旅行、とくに時計の発表会や何かを取材する目的がない旅行は断ることにしている。実際のところ、オリンピックではオメガによって実現した“世界最速の男”の写真撮影や、世界記録達成の際に公開された新しいスポーツウォッチ、さらにはダニエル・クレイグ(Daniel Craig)の手首にあった新しいシーマスター 300Mのお披露目など、時計にまつわるニュースは多くあった。だが信じてもらえない人たちに対しては、正直にこう言うしかない。
Olympic Chronoscope
オメガスーパーコピー 代引き スピードマスター クロノスコープ パリ2024エディション
実際にオリンピックを目にすることで、競技そのものやアスリートたち、そしてオリンピックが意味するものへの愛情と敬意がさらに深まった。もしオメガへの愛が増したとすれば、それはほかの時計に対する愛がいつもそうであるように、結局は“人”によるものだったのだと思う。オメガファンだけでなく、世界中から集まった情熱的なファンの大群に囲まれたことが、オリンピックをまったく新しい次元に引き上げてくれた(観客の大歓声で永続的に耳を傷めてしまったかもしれないが、その経験も含めてだ)。
Omega Speedmaster Mk40
このモデルこそが、HODINKEEのすべての始まりとなったオメガ スピードマスター マーク40である。希少でもなければ高価でもないが、重要なのはそのストーリーなのだ。
結局のところ、人々こそがストーリーテラーであり中心なのだ。“最も重要なムーブメント”や“最も美しいモデル”から、“私にとっていちばん大切な時計”まで、すべての最上級表現はストーリーから始まる。オメガとともに参加したオリンピックで出会ったコレクターや小売業者、同僚たちから感じ取ったのは、オメガというブランドと時計に対する情熱と興奮だった。彼らは実に希少で、ときに珍しい時計を持ち出してきた。しかし私が出会ったすべての人が証明してくれたのは、話題性や投資収益のためではなく、それぞれの時計が持つストーリーと、所有者にとって特別な存在となるディテールが重要だということだった。いつも言っていることだが、すべての時計を集める余裕がなくても、少なくともそのストーリーと知識は集めることができる。そしてオリンピックで出会った人々は、そのストーリーをよろこんで共有してくれた。
Olympic timing watch
1932年のオリンピックで使用された、初期のスプリットセコンドクロノグラフのひとつがパリのオメガハウス(特別なイベントスペース)に展示されていた。
ある意味で、オリンピックにおけるオメガの役割は舞台裏に自然に溶け込むことだ。それはこの92年間、主に“公式タイムキーパー”としてオリンピックを支えてきた役割でもある。確かに1964年、1972年、1992年、1994年にはセイコーが計時を担当したが、オメガは2032年の100周年まで公式タイムキーパーを務める契約を結んでいる。この92年のあいだに状況は大きく変わった。1932年の大会では、オリンピック会場にひとりの時計職人と30個のスプリットセコンド懐中時計が配置され、10分の1秒を計測していたが、2024年には1秒間に4万コマを撮影するカメラと1000分の1秒を簡単に計測できるタイマーが登場するまでに技術が進化した。パリのオメガハウスに展示されているのは、まさにその1932年当時の懐中時計のひとつである。
Photo finish
男子100m決勝のフォトフィニッシュ。Photo: courtesy of Omega
もちろん、オメガのブランディングは随所に見られるが、パリに設置されたオメガハウス(社交クラブと博物館を兼ねた施設)以外では比較的控えめだ。それはオメガブランドのテクノロジーにも同様に言える。その技術の多くはスウォッチグループ傘下のスイスタイミング社によるもので、オメガだけでなく、ロンジンなどのブランドにも提供され、さまざまなスポーツイベントで活用されている。実際に意識して探さない限り、目立つことはない。肝心なのは目立つことではなく、アスリートたちの何年にもわたる努力を台無しにするような機材トラブルを避けることだ。そして世界最高のアスリートが誰かを決める瞬間が来ると、オメガはその場に立ち会い誰かのストーリーに貢献する。
Omega Seamaster sign
ダニエル・クレイグ氏がノンデイトのシーマスター 300Mを着用していることについて記事を書いた翌日、会場周辺にある時計がどこか見覚えがあるのに気づいた。
Omega Lollipops
先週パリにいたなら、オメガの“ロリポップ”を見かけているかもしれない。ビザやNBC、そのほかのスポンサーの看板と並んで、いろんな人たちが目的地に辿り着くのを助けていた。
パリから持ち帰りたかったのは(ギフトショップで購入した十数個のピンバッジに加えて)、オメガが使用する計時技術に関するストーリーだった。しかし現地にいた48時間ではそれを間近で見ることは叶わなかった。それは数年後まで待つことになるだろう(編注;HODINKEE Japanではオメガタイミングの記事を掲載している)。皆を一緒に連れて行けたらよかったのにと思う。もしかすると、すでに自分で行った人もいるかもしれない。ただ私が短い時間で目にした最もクールな時計や瞬間をまとめたPhoto Reportを見ることで、少しでもその場にいた気分になってもらえたらと思う。時計に対してもオリンピックそのものに対しても、あの場で感じた情熱の一端でも伝われば幸いだ。
1日目: スピーディとビーチバレー
Omega Tokyo Rising Sun Olympics Speedmaster
前回の夏季オリンピック(少なくとも時計に関して)の話に戻ろう。フラテッロのロバート=ヤン・ブロア(Robert-Jan Broer)氏が着用していたオメガ スピードマスター“ライジングサン”東京オリンピック限定モデル、Ref.522.30.42.30.06.001。これは2日目のスタートに彼が選んだ時計だった(もちろん彼はスピードマスターを複数本持参していた)。
River Seine
オメガハウスから少し歩き、バスに乗ってセーヌ川を下ると、開会式が行われた数々の場所を目にすることができた。
Omega Chronoscope Olympics
オリンピックのためにつくられたオメガ スピードマスター クロノスコープをもう1度。時計よりも手首につけた様子を見せたくて投稿したかった。
Reynald Omega
手首はオメガCEOであるレイナルド・エシュリマン(Raynald Aeschlimann)氏だった。彼はいつものように、セーヌ川を下るあいだに率直な感想をいくつか共有してくれた。
CK 2998
オリンピックにおいて、時間を計測するスピーディは最も理にかなっているかもしれないが、自分がどれだけハードに働いているかを知りたいなら2018年限定のオメガ CK 2998のような時計を試してみるのもいいだろう。
Omega Constellation
オリンピックで見かけたのはスピードマスターだけではなかった。こちらは珍しくてあまり見かけないオメガ コンステレーション ダブルイーグル クロノグラフ“ミッションヒルズ”エディションで、サウジアラビアから来た新しい友人、シェイク・モハメド・アル=フセイニ(Sheikh Mohammed Al-Hussaini)氏の手首に輝いていた。
Seine
セーヌ川を下り、グルネル橋にある自由の女神像の周りを回ったあと、再び川をさかのぼった。
Eiffel Tower
Eiffel Tower
Olympic Seamaster
オリンピックのために登場した、新しいシーマスター 300Mをつけていたのは、子供たちが言うところの“しっかり準備した”コレクターだった。
304.93.44.52.99.002
船を降りる前に、まさか見られるとは思ってもみなかった時計に出合った。それは台湾のコレクターが手首につけていたスピードマスター ムーンフェイズで、プラチナゴールドのケースに赤いアルミナ製のベゼルリング、サテン仕上げのプラチナ製リキッドメタルタキメーターとルビーのインデックスが特徴的なモデルだった。
Speedmaster
もちろん、定番のスピードマスターもたくさん見かけた。
Speedmaster “From Moon to Mars"
さらに個性的なモデルも登場した。たとえばスピードマスター“フロム ムーン トゥ マーズ”のRef.3577.50.00のようなものだ。この表現、少し洒落が効いている。
Wei Koh Silver Snoopy
このタトゥーに見覚えがあるかな? そうウェイ・コー(Wei Koh)氏だ。彼の手首にはシルバーのスヌーピー スピードマスターが輝いていた。
Sedna Gold Speedmaster
なかには金メダル、つまりセドナゴールドを選んだ人もいた。たとえばスピードマスター Ref.310.60.42.50.01.001とか。
View of the Volleyball Park
エッフェル塔に登ると、ビーチバレーの競技が行われているエッフェル塔公園の景色が一望できた。
- 2025年08月25日(月)11時07分
- 前のページ
- 次のページ